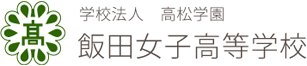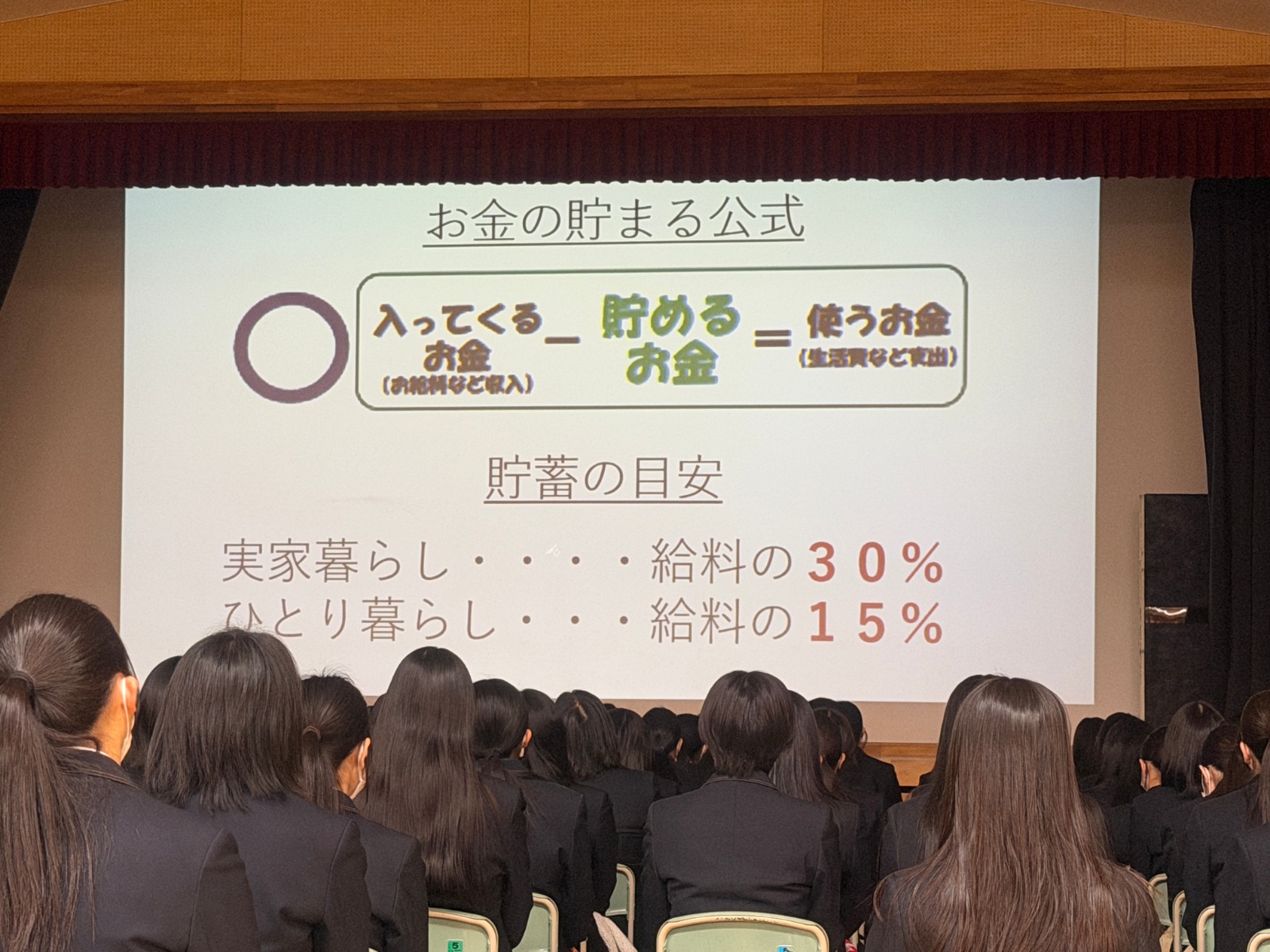【探究通信】11月20日「本当の課題を見抜く力」とは
今日は「本当の課題を見抜く力」というテーマで講演をお聞きしました。とても面白い経歴をお持ちの、国際エデュテイメント協会代表理事の森俊介さんにオンライン登壇して頂いての開催となりました。

さっそく森さんから一つの問題がだされました。
お店にやってきたお客さんが「6㎜の高性能ドリルはありますか?」と聞いてきました。
店員は「今、品切れです」と答えました。
「‥‥(お客さんは帰ってしまいました)」
さて、あなたが店員だったらどう対応しますか?
→他のお店から取り寄せられるかきいてみる
→今日は品切れだけど、入ったらお知らせする
→予約されるか聞いてみる
生徒のみなさん、なかなか店員っぽく答えています。
「ドリルを買いに来た人が欲しいのはドリルではなく、『穴』である」
これはマーケティングを考える上で有名な格言「レビットのドリルの穴理論」というそうです。この時、お客さんが抱えていた課題とはなんだったのでしょう?ドリルがなかったから欲しかったのでしょうか?とにかく穴をあけたかったのでしょうか?
もし、店員が「何に使われますか?」など用途を聞いていれば、ドリル以外にお客さんの抱える課題を解決する提案ができたかもしれません。
見えている現象と本当の課題は違うかもしれないという例でした。


森さんは本当の課題をとらえるために必要なのは「課題のリフレーミング」、課題や状況を新しい視点で考えること、つまり発想の転換が必要だとおっしゃいました。
例えば、エスカレータ―ばかりに人が殺到。階段はガラガラ…。この解決のために、階段が楽しくなればいい!とピアノ階段(歩くと音が鳴る)を提案・設置した駅があるそうです。
なるほど、おもしろい!
続けて森さんはこう話してくれました。
「発想の転換。これはセンス?いや違う!鍛えられるものです!」と。
・トヨタでも採用されているなぜなぜ分析。
・世の中の現象をうのみにせず、いったん自分で疑ってみる。
・動画は視覚的にわかりやすい。でも他の人と同じイメージしか抱けない。読書は妄想ができる。自分の軸で判断する力をつけられる。
森さんが教えてくれたことは難しいことではなく、今からでもできることではないでしょうか?
今日は「本当の課題を見抜く力」を身につけるためのヒントを森さんがたくさん下さいました。自分の身近な課題、国や世界で考えないといけない壮大な課題、世の中には様々な社会課題があふれています。今日の講演のおかげで「難しい…」で終わってしまう課題に対しても、発想の転換でもう少し、食いついていけそうな気がしました!生徒のみなさんはどうでしたか?