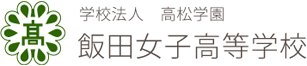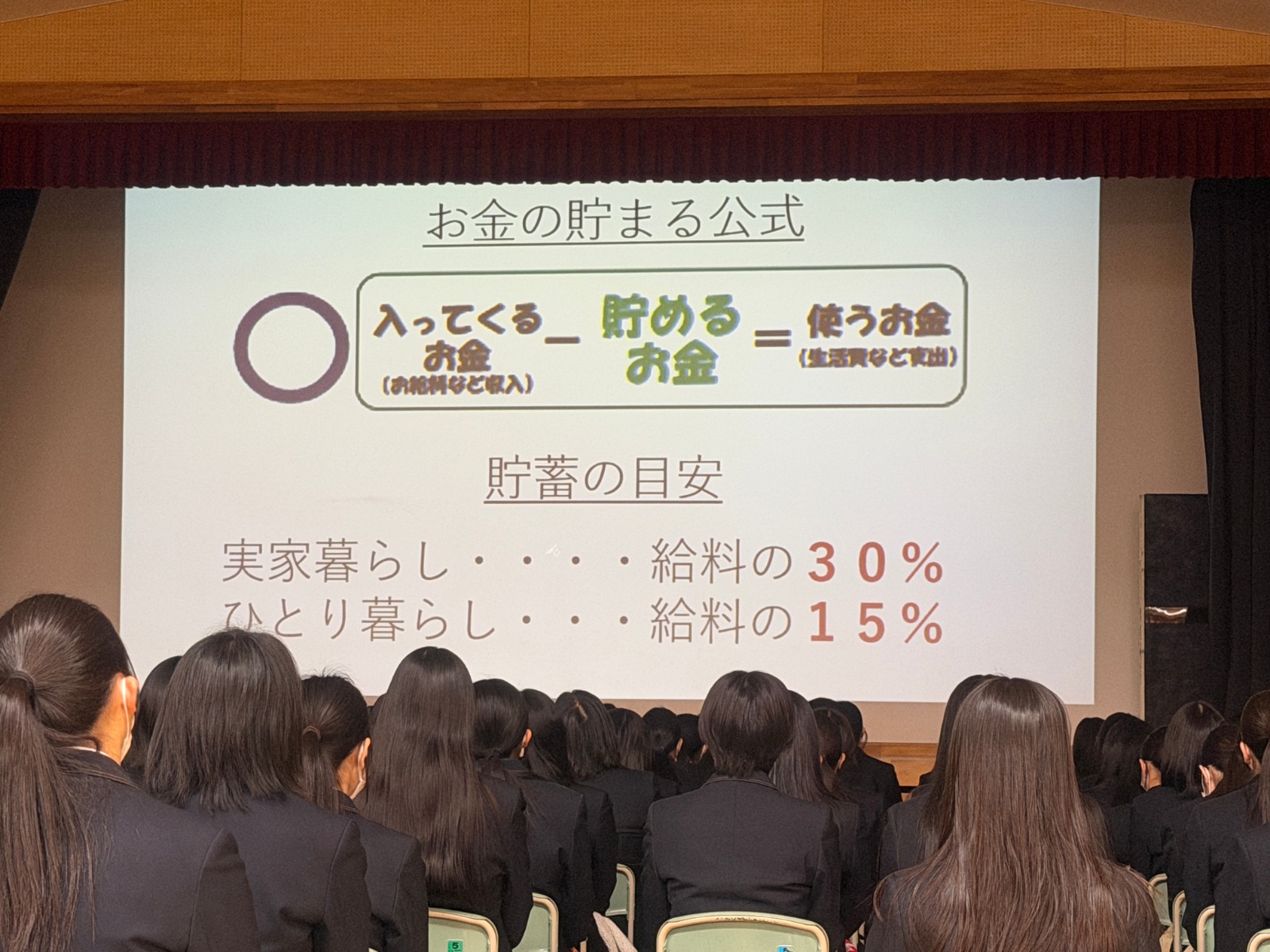地学基礎 実験探究「歩いて地球の大きさを測ろう!」

先週から今週にかけて地学基礎の授業では、「歩いて地球の大きさを測ろう!」という実験を行いました。
「え!そんなことができるの!?」って声が聞こえてきそうな実験ですね。
古代ギリシャの哲学者エラトステネスは、自分の歩幅の長さを測定し、歩くことで2地点間の距離を測りました。これを歩測といいます。(エラトステネスはこのとき925kmも歩いたそうです)
2地点間の距離がわかれば、
(2地点の距離):(2地点の緯度の差) = (地球の円周):360°
と、比を用いて地球の円周を知ることができます。
エラトステネスは、この実験で地球の円周がおよそ4万6000kmであると計算しました。実際の地球の円周は4万kmなので誤差は15%しかなかったそうです。
人工衛星もない時代にすごいですね!

エラトステネスは、太陽の角度から緯度を計算したのでとても長い距離を歩きましたが、地学基礎の授業ではGPSを使うことで5分ほど歩くだけで、地球の大きさが計算できます。現代の測定技術はすごいですね!
ある生徒は地球の大きさを計算した結果およそ4万6百kmとなりました。(ぱちぱち👏)
日頃は考えない私たちの住む「地球」。
地球は本当に丸いのか⁈
丸みを感じながら生活したことはあるのか⁈
こらからの授業でさらに深く「地球」を知っていきます!